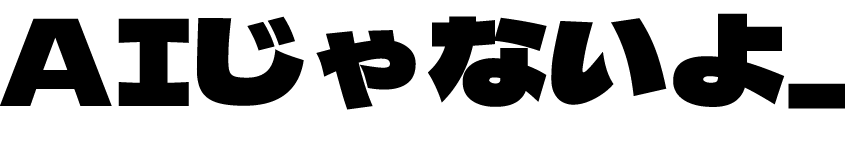2025年7月24日、GoogleがAIアプリをノーコードで容易に開発できるツール「Google Opal」をリリースした。
プログラミング知識がなくとも、ユーザーインプット→複数のAIモデル/ツールのチェーン→結果の出力という一連の流れで構成されるアプリケーションを、チャットとマウス操作だけで、超簡単に構築することができる。
オープンソースのノーコードAIアプリ開発ツール「Dify」のような機能を持つものだが、Google のサービスだけあって、Googleドライブなどとスムーズに接続できる。
将来的にGoogle Workspaceと統合されたりすれば、様々なビジネス向けAIミニアプリが誰でも簡単に作れる未来がやってきそうで、夢が広がる。
ただし、残念なことに、Google Opal は2025年7月現在は米国限定でテストが行われている段階であり、普通には日本から利用することができない。
本記事では、そんなGoogle Opalを、日本から使用するための裏技を紹介する。
無料で試すことができるので、Google Opalのニュースを目にしたが、日本から使用できずもどかしい思いをしている人に、ぜひ参考にしてもらいたい。
Google Opal の概要
Google Opal は、自動化したい手順を、ビジュアルで分かりやすいワークフロー図の形式に整理するだけで、実際に動作するAIミニアプリを作成できるツールだ。
まるでパワポスライドを作るかのように、実際のアプリを開発することができる。
例えば、Google公式が提供しているサンプルアプリの一例を紹介すると、以下の画像のような、自動でブログ記事を執筆してくれる「Blog Post Writer」というアプリがある。

「Blog Post Writer」アプリは、上の図の通り、最初にユーザーが入力したトピックを、左から右に向かって順に処理を重ねていくワークフローで構成されている。
ユーザーからトピックを受け取り、Web検索を行い、検索結果の要約を作成し、それに基づき記事を執筆し、同時にバナー画像を生成し、最後に完成した記事を表示・・・という一連の流れを、全て自動で行なってくれるのだ。
これらの各アクションが、AIモデル/ツールが連鎖するワークフロー図によって繋げられている。複雑なアプリが、プログラミング知識不要で、ノードを線で繋ぐだけで作成できるのだ。
ノーコードでのAIアプリ開発が、非エンジニアも含めて、急速に普及しそうな期待が持てるツールだ。
日本語で指示するだけでアプリが瞬時に完成
Google Opalには、ユーザーが自らワークフロー図を描くだけでなく、作りたいアプリのイメージを日本語で入力すると、それを踏まえてGeminiがワークフロー図を勝手に考えてくれる機能までついている。
ワークフロー図を考える手間すらも省いてくれて、日本語が使えるユーザーであれば、誰でも瞬時にアプリ開発が可能になってしまう革命的な機能だ。
試しに、「ユーザーが指定したオブジェクトを動画にするアプリ」と指示を与えてみる。

すると、わずか数秒で、「ユーザーインプット→Geminiによる動画生成プロンプトの生成→Veoによる動画の生成」という複数のAIモデルを組み合わせたワークフローが、自動で完成した。

ワークフロー図ができたら、即座に実際に実行することが可能だ。画面右側に、アプリの実行画面が現れ、左側で作成したワークフローの順番通りに、アプリが動き始める。
まず、どんなオブジェクトを動画にしたいかを聞かれたので、試しに「バナナ」と答えてみた。

すると、動画生成プロンプトの作成、動画の生成という2段階のステップが自動で実行されていき、無事にバナナのビデオが生成された。

これは非常にシンプルな例であるが、GoogleドキュメントやGoogleスライドへの結果の出力なども可能なので、もっと複雑な業務自動化アプリも、簡単に作ることができるだろう。
Google Opal は裏技なしでは日本から利用不可
Google Opal は、Googleアカウントがあれば、誰でも無料で利用することができるようになっている。
かつて、今日では製品版としてリリースされている「NotebookLM」が実験的にリリースされた時と似たような形で、あくまで「実験版」として公開されている。
ただし、日本から「Google Opal」のページに接続すると、以下のように「Opal is not available in your country yet」と表示されてしまい、アプリの作成に進むことができない。

これを回避するには、米国から接続する必要があるが、その時に活躍するのがVPNサービスだ。
日本からGoogle Opalを使う裏技:米国VPNを経由して接続
VPNは、NetflixやHuluなどのリージョンロックを回避する方法としてもよく使われる手段だ。
一般に、米国サーバーのVPN接続を経由することで、米国からアクセスしているかのように見せることが可能である。
実際、米国のVPNに接続した状態で、Opalのサイトにアクセスしてみると、地理制限を回避でき、無事にOpalのベータ版の画面が表示された。

筆者が複数のVPNでGoogle Opalの動作確認を行い、無料で利用できるオプションと、有料かつ高速に利用できるオプションを見つけたので、それぞれ紹介しておく。
無料でも利用できる米国サーバーのVPNとしては、「Hotspot Shield」というアプリがある。Freeプランであれば、端末1台まで無料で米国サーバーを利用できる。
Mac, Windows, iPhone, Androidなど各OS向けにアプリが用意されているので、「Hotspot Shield」のアプリをダウンロードして、「Virtual location」でアメリカを選択する。
その状態で、Google Opalにアクセスして、Google アカウントでログインすると、Google Opal が使えるようになっているはずである。

Google Opal を使用するだけであれば、それほどアップロード/ダウンロードの回線速度は早くなくても良いので、無料版のHotspot Shieldだけでも何とかなる。
ただ、同時に背後で作業をしたり、ファイルのダウンロードをしたり、How To 動画を見たりする場合には、若干回線スピードが気になる可能性はあるので、その場合は有料のVPNサービスを活用しても良いだろう。
筆者は、「NordVPN」を利用しており、NordVPNの米国サーバーに接続した場合でも、Google Opalに問題なく接続できた。

AIノーコードアプリツールの業界標準になりうる完成度の高さ
実際に Google Opal を触ってみた感想としては、実験版といえど、非常に完成度が高く、業務効率化ツールの世界に革命が起こりそうな予感だ。
ドラッグ&ドロップだけで、数分でアプリが作れてしまう体験は、一度味わったらハマってしまうこと間違いなしだ。
Difyのような複雑なインストール作業も不要で、Googleアカウントさえ持っていれば瞬時にアプリの作成を開始でき、完成したアプリは瞬時にウェブ上にデプロイされる。
まるでGoogleドキュメントのように、作成したアプリはチームメンバーに簡単に共有することもできる。

コードやインフラ準備の手間がゼロになるので、ちょっとした業務効率化アプリの作成や、アプリ開発のプロトタイピングなどが、非エンジニアのホワイトカラーにも普及し、急激に民主化する可能性がある。
GoogleドキュメントやGoogleスプレッドシートのようなノリで、誰もが簡単にGoogle Workspace上でミニアプリを作れるようになれば、生産性向上効果は計り知れない。
Gemini 2.5 Pro / Deep Research など上位モデルも無料で使えてお得
現時点では、Gemini 2.5 Pro、Deep Research、動画生成のVeo、音楽生成のLyrla 2など、Google の開発する各種AIモデルの上位版・実験版なども、Opal内で幅広く無料で利用できるので、単純にAIツールとしてお得感もある。

画面下部のチャットウィンドウで、自然言語でワークフローの作成をGeminiに依頼できるので、「シンプルなディープリサーチツール」と言ってみると、以下のようにDeep Researchの結果を表示してくれるだけのシンプルなミニアプリも、わずか数秒で作ることができた。

最初は、複雑なワークフローを作らずとも、単純にGoogleのAIモデルを使って音声、動画、画像を生成するだけのアプリなど、単機能のツールとして使ってみても楽しいはずだ。
早く日本向けに公式リリースされることを祈りつつ、しばらくはVPN経由で、ひと足先にノーコードAIアプリ開発の世界を体験してみてはどうだろう。