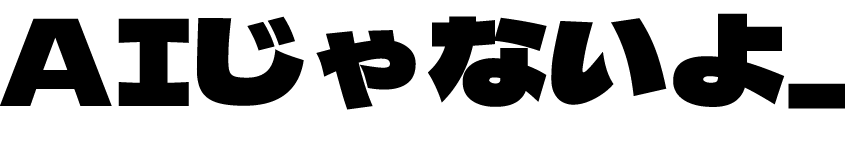ライター・プログラマーとして、手首や指の痛みに長年悩まされ、これまで6台のメカニカルキーボードを渡り歩いてきた筆者が、ついに全ての悩みを解消する究極のキーボード「Glove80」に出会ってしまった。
長時間のタイピングによる手首や指の痛みに悩む方で、HHKBやリアルフォース、メカニカルキーボードの購入を検討したことのある人は、ぜひ「Glove80」のようなエルゴノミクスキーボードを候補に入れるべきだ。
MoErgoの「Glove80」は、数あるエルゴノミクスを謳ったキーボードの中でも、お椀型、左右スプリット、オーソリニア配列(カラムスタッガード配列)という非常に特殊な形状をしている。
細部まで徹底してエルゴノミクスにこだわってデザインされており、朝から晩までタイピングし続けても疲労や痛みがほとんどなく、他社のキーボードとは全く別世界の打ち心地を味わうことができる。
沢山のキーボードを所有してきた筆者だが、「Glove80」を使い始めてからというもの、オフィスや出張にも持ち歩くほど気に入っており、仕事で手放せない一品になっている。快適すぎて、他のキーボードを使用するのがストレスになる程だ。
上級者向けっぽい見た目に反して、意外にもすぐに慣れるので、キーボードの買い替えを検討している人は、選択肢に入れて良いと思う。
カスタムキーボード界では珍しく、「Glove80」は技適も取得しており、日本国内でのBluetooth使用が可能となっており、日本ユーザーには最適な選択肢だ。
キーボード沼の結論:基本構造が同じキーボードを何台持っていても意味ない
筆者は7-8年前からキーボード沼に足を踏み入れ、メカニカルキーボードだけでも6台は所有している。キーキャップやキースイッチのグループバイに参加したり、カスタムキーボードを購入してみたり、キーボードに投資してきた金額は大きい。
しかし、筆者は職業柄、あまりに長時間タイピングをしているせいか、どんなに高級なキーボードを買っても、結局、手首や指の痛みに悩まされ続けてきた。
ライターとして1日1〜2万文字を超える執筆をすることも珍しくなく、また日常的にプログラミングも行うため、手首や指に痛みが生じやすく、長時間の作業が辛くてしょうがない。
ここ数年は、一般的なパンタグラフ式キーボード、ハイプロファイルのメカニカルキーボード、ロープロファイルのメカニカルキーボードの3台を、1日の中で何度かローテーションすることで、手首や指にかかる負荷を分散させ、腱鞘炎などを予防してきた。

しかし、悩みに悩んだ末に至った気づきは、何台キーボードを買い替えようが、「キーボードの基本構造が同じであれば、根本的な問題は解消されない」ということだ。
一般的なキーボードは、机の中心に両手を集めるため、常に手首に不自然な角度がつくし、猫背になりがちになる。また、小指がやたらと働かされ(Ctrl、Shift、Enter、Backspaceなど)、ホームポジションからの無駄な移動や手首の曲げ伸ばしも多い。

そうして探し始めたのが、人間工学に最適化して設計されたエルゴノミクスキーボードだ。
元々、左右分割キーボードなどに興味はあったが、なぜか日本国内で販売されているスプリットキーボードは、40%など極端にキーの数を減らした玄人向けばかりで、普通にフルキーボードが欲しい筆者としては躊躇していた。
そんな中、左右分割・お椀型という人間工学の極致のようなデザインでありながら、ファンクションキーや矢印キーを備え、十分な数のキーがある理想的なキーボード「Glove80」に出会った。
筆者が求めていたすべての条件を満たしていることから、日本語での情報が殆どなかったが、手首や指の痛みから解放されるべく、試してみることにした。
Glove80 はなぜ最高なのか:エルゴノミクスキーボードの利点

結論としては、MoErgo Glove80は、マジで最高なキーボードだった。
長時間タイプしても驚くほど疲れることがなく、手首や指の疲労感が解消しただけでなく、猫背や肩こりなどにまで影響があると感じた。
Glove80を使い始める前は、右手の小指側に慢性的な痛みを感じていたのだが、Glove80に完全移行してから、手指の不快感が解消した。個人差はあるだろうが、実際に疲労感や不快感の改善が体感できている。
さらに、思わぬ効果として、タイピング速度が人生最高のスピードに達し、ミスタイプも減った。
非常に特徴的なレイアウトをしているため、タイピングに慣れるまでに時間がかかるかと思ったが、1週間ほどで徐々に慣れ、3週間もすれば元のキーボードより快適に使えるようになった。
以下、そんな「Glove80」がもたらしてくれたメリットの数々を、人間工学的な観点とあわせて、詳しく紹介していく。
左右スプリットのおかげで、猫背まで改善
長年使い慣れてしまって違和感を持ちにくいが、通常のキーボードは、長時間使用すると手首に一定の負荷が掛かってしまう。
体の中心に両手を寄せてタイピングするため、手首が外側に向かって無理な角度がついた状態になっている。この状態で毎日8時間超もデスクワークをしていたら、負担が蓄積して不調が生じるのは当然だ。
左右スプリット型のキーボードであれば、両手をリラックスした状態で配置することができ、手首に無理な角度がつきにくいのが大きなメリットだ。

さらに、これは実際に左右分割型のキーボードを使い始めて気付いたことだが、手首だけでなく、猫背や前傾姿勢を防ぐ効果もある。
例えば、机の上に両腕を置き、肩幅に開いた状態で、猫背にしようとしてみてほしい。当然だが、両手を肩幅に開いた状態では、そもそも猫背になることができないのだ。
通常のキーボードでは、体の中心に両手を寄せることになるため、心がけていないと自然と猫背になってしまい、前傾姿勢になりがちだ。

一方、左右スプリットキーボードで、肩幅に手を開いた状態では、姿勢を全く意識していなくても、猫背や前傾姿勢を防いでくれる。
筆者は普段かなり姿勢が悪いので、姿勢改善効果の恩恵を最大限に享受している。

そもそも、毎日8時間以上も連続で使用する両手用のデバイスが、左右に分かれてないこと自体がおかしいのだ。
使い始める前は、適応できるかどうか最も不安だったのが左右分割レイアウトだが、思いの外、何の違和感もなく移行することができ、今ではすっかり手放せなくなった。
お椀型&オーソリニア配列で、指・手首の動きを最小化
Glove80の最大の特徴は、やはりお椀型の湾曲デザインだ。指の自然な動きに沿って湾曲しており、タイピング時の移動距離を小さくしてくれる。
実際、以下の写真のように、通常のキーボードだと手首を動かさないと届かない数字キーに、ホームポジションから指をちょっと曲げた状態でも届く。
手首を動かすことなく、全ての数字キーまで指が届くのは、結構驚きの体験だ。

最下段にある矢印キーなどにも、手のひらを自然にグーの形に丸めるだけでタッチできるので、ホームポジションでタイプできるキーの数が大幅に増える。
手の大きさにもよるだろうが、筆者の場合、ホームポジションから全く手首を移動させずに、Functionを除くほぼ全てのキーに指が届く。

また、Glove80は、キーが縦一直線に並んだ特殊なキー配置になっている。これにより、指を曲げたり伸ばしたりするだけでタイピングが可能で、お椀型のシェイプも手伝って、指の移動距離が最小限に抑えられる。
通常のキーボードは、行が互い違いにズレた「row staggered(行ずれ)」配列と呼ばれる。
いまだに現代でも一般的だが、1800年台のタイプライターの時代に、機械の打鍵が絡まないようにキー同士をズラしたことが起源であり、左右斜めの無駄な移動が多く、人間には何らメリットがない。

これに対しGlove80は、指の長さに合わせて列の位置がズレた「column staggered(列ずれ)」配列だ。
例えば小指が担当する列は、他の列より低くなっており、小指をグーの形に握った時に、自然にタイプできる位置にキーが配置されている。

Glove80は、単なる「column staggered(列ずれ)」から更に一歩踏み込んで、中指のキーが”奥”にあるなど、3次元的に列がズレているため、「3D-column staggered」とでも呼ぶべき究極の配列だ。
手首の上下の曲げを徹底的に抑えたデザイン
また、Glove80でタイピングする手を横から見ると、前腕から手首が水平になっていることがわかる。これを「ニュートラルティルト(Neutral Tilt)」と呼ぶ。
どの位置のキーを打っていても、ニュートラルティルトのポジションが維持されており、通常のキーボードで頻繁に生じる手首を上方向に曲げる動きを防いでくれるため、長時間の作業をしても疲労や痛みが生じにくい。

また、Glove80は、いわゆる「ロープロファイル」キースイッチと呼ばれる Kailh Choc v1 スイッチを採用している。
ロープロファイルスイッチ(写真左)は、通常のMXスイッチ(写真右)と比べて、スイッチの背が非常に低い。押下時の指のストロークが減るほか、手首を「低空飛行」させることで上方向に曲げる必要が減るため、手首の負担も減る。

AppleのMagic Keyboardなど薄型キーボードを使用していた人が、気合を入れてHHKBやメカニカルキーボードを買ってみたら、むしろ疲労や手首の痛みが生じてしまった、というトラブルは、キーの高さと手首の角度が原因なのだ。
Glove80は、キー位置が非常に低く、また全体が湾曲しているおかげで、どのキーを押す場合でも、手首の伸展(上向きの曲げ)が殆ど必要ない。
パームレストに手首を置いた状態から、手首を上げ下げすることなく、先述の「ニュートラルティルト」ポジションを維持することができる。

通常のメカニカルキーボードと比べて、非常に長い文章をタイピングした場合などには、明らかに疲労感が軽減するのを感じられる。
湾曲型、低いキー位置、パームレストと、Glove80の徹底して手首に無駄な角度をつけない設計は、人間工学的に考え抜かれていると感じる。
従来のキーボードでは活用できていない「親指」が大活躍
従来のキーボードは、力の弱い小指に、多数のキーを担わせ過ぎている。
筆者自身、Ctrl+C/Vでコピペ、Ctrl+Zで元に戻すなど、小指を使うショートカットを多用しているせいで、腱鞘炎のような状態になった経験が何度もある。
一方で、最も強力なはずの親指は、無駄に長いスペースバーを押すだけで、ほぼ無駄になっている。
その点、Glove80は、左右の親指に6つのキーを割り当てた独特なレイアウトだ。これを「Thumb Cluster (親指クラスター)」と呼ぶ。

親指の自然な弧に沿った配置になっており、手のひらを移動させずに、6つのキーすべてに到達可能だ。

最も力の強い親指でSpace, Enter, Backspace, Delete, Shift, Controlなどの修飾キーを担当し、キーボードショートカットも親指を起点にして発動するので、小指の負担を大幅に下げることができる。
また、親指クラスター内に12個もキーがあるので、英字・かなの切り替えなどの日本語環境特有の特殊キーも配置する余裕があり、キーが少ない一般的なUSキーボードでは叶わない快適な使い心地を実現できる。
自然なテンティングによって手首が楽に
フラットなキーボードを使っていると、常に手のひらを下向きにひねったような不自然な状態になっている。
例えば、机の上に手のひらを付けておいてみると、手首から前腕にかけて若干の緊張を感じるはずだ。これもまた、長時間のタイピングをすると手首や腕に負担がかかる原因の一つだ。

キーボードを斜めに傾けることをテンティングと言い、自然に腕を伸ばした状態(握手のポジション)に近づけることができる。

Glove80は、下部にネジ式の脚がついており、これを伸ばすことで、好きな角度のテンティングを設定することが可能だ。
角度をつけずとも、デフォルトで自然な傾斜がついているので、必要がなければ、わざわざテンティングをする必要はない。
以下の写真は、デフォルトでついている脚を伸ばした状態と、伸ばしていない状態だ。この程度の差でも、結構感覚が異なる。

無段階調整が可能というメリットを活かして、様々な角度を試してみながら、自分が最も楽に感じるポジションを見つけることができる。
後に詳述するが、テンティングのカスタマイズ性の高さも、Glove80の魅力の一つである。付属の長いM4ネジを使って、さらに角度を強くすることも可能だし、ロックナットを使って一度決めた角度を固定することもできる。
Glove80 詳細レビュー:開封からセットアップまで
以上では、エルゴノミクス的観点からみた主要な特徴をざっくり紹介した。
ここからは、外観デザインや付属品、購入時のオプション項目(キースイッチの種類やアクセサリー)、ファームウェアなど、委細について解説していく。
本体デザインや付属品・トラベルケース
Glove80はニュージーランドと日本のデザイナーによって作られ、中国から発送されてくる。標準で以下のようなトラベルケースが付属し、しっかり守られて送られてくる。
ケースは頑丈な上、テンティングしたまま収納も可能なので、このまま出張や旅行に持っていくことも可能だ。

キーボード本体はプラスチック製で、見た目のボリュームに反して、左右合計の重さは580gと非常に軽く、ペットボトル飲料1本分の重さで手軽に持ち運ぶことができる。
軽量ながら安定しておりガタつきは全くなく、筆者はGlove80をバックパックに詰めて頻繁に出張や旅行で持ち歩いているが、耐久性にも全く問題ない。
背面には電源スイッチを備えており、指先で触れただけでオンオフが分かりやすく助かる。

また、RGBバックライトも備えており、単色の点灯やレインボーアニメーションなど、複数の点滅パターンや色の変更が可能だ。

RGBは、見た目の演出だけでなく、充電量やBluetoothステータス表示にも使用される。左手側のキーボードのRGBが、ステータス表示を兼ねている。

また、付属品として、USBケーブル、テンティングの最大角度を変更するためのM4ネジや脚底部、脚の長さを固定するためのナット、ネジが緩むのを防ぐOリング(小さい輪ゴム)、予備のキーキャップ(Mac用やF12キー等々)、キーキャップを外す道具などが同梱されている。

テンティングの角度の調整
Glove80の本体裏の脚部は、M4ネジによって長さを調整できるようになっており、無段階で柔軟なテンティング・アングルの設定が可能である。
独自規格でなく、一般的なM4ネジなので、椅子などへの固定をはじめ、カスタマイズの幅が広いのも魅力である。
付属品として、より長いM4ネジが同梱されているので、より強い角度でのテンティングを実現することもできる。

デフォルトの脚を最大限に伸ばした角度と(写真右)、付属品の長いM4ネジを最大限に伸ばした角度(写真左)を比較したのが以下だ。
テンティングは個人の好みの差が大きいので、ネジを変えることで幅広いニーズに対応できるのはありがたい。

また、付属のナットやOリング(輪ゴム)を使って各脚を固定すれば、いつも使うテンティングの角度で固定し、ネジが緩むのを防ぐことも可能だ。自宅のデスクで使っている、という人は、固定してしまうのがベストだろう。
一方で、筆者のように、出張や出勤に持ち歩くなど頻繁に移動する人は、片付けるたびにネジを締めたり緩めたりする必要がある。
そのような場合は、手間なく瞬時にいつもの角度を復活させる方法として、M4規格の「ナイロンインサートロックナット」を活用する方法がある(※ナイロンナットは別売)。
ロックナットは、ナットの内側にゆるみ防止のナイロンが入っており、かなり力を入れないと回らないので、好みの長さで一度固定すれば、脚をつけたり外したりしてもズレることがない。

移動時には、ネジを外した状態で持ち運び、組み立て時にナイロンロックの位置までネジを締めれば、いつもの角度を瞬時に再現できる。持ち運びのコンパクトさと、外出先での利便性を両立することができるのでオススメだ。
ちなみに脚だけでなく、パームレストも容易に取り外しが可能なので、出張時には各パーツをTシャツなどに包んでかなりコンパクトに移動することも可能だ。

交換可能なキーキャップで新配列に慣れやすい
メカニカルキーボードによっては、列によってキーキャップの高さが異なっており、キーキャップを相互に交換できないものも多い。記号の位置などレイアウトを変更すると、キーの印字と実際の出力が異なってしまうのがよくある悩みだ。
その点、Glove80は均一プロファイルで、全てのキーキャップが相互に入れ替えられるのが大きな利点だ。
慣れない新配列のキーボードでは、初期の頃はキーの位置が思い出せず結構ストレスがかかるので、キーの印字と配列が一致しているのは非常にありがたかった。
キーのレイアウトの変更を行った際にも、キーキャップの配置もそれに合わせて変えられるため、記号の位置などで混乱が少ない。

Glove80のキーキャップは、かなり珍しいPOM(ポリオキシメチレン)素材で作られている。
POMは、ABSやPBTなどの一般的なキーキャップよりも製造コストが高いプレミアムな素材で、経年による光沢や摩耗が少ないのが特徴だ。キーボードを長く使用していると、よく使うキーがテカテカしてくることがあるが、大抵は安価なABSを使用しており摩耗が早いことが原因だ。
キーキャップの素材ひとつとっても、長く愛用できるように作られていると感じる。

キーキャップの形は、円筒形の凹面形状である「MCC」プロファイルだ(写真左)。垂直方向の指の動きがスムーズで、これもGlove80の人間工学に配慮されたデザインの一環だ。
なお、凸面形状の「MBK」キーキャップが2個付属品としてついてくる(写真中央)。指で触った時にエッジを感じるため、これをホームポジションの補助や、親指の位置を把握するための補助として利用できる。
また、オプションのアクセサリーとして、MCCキーキャップにドットの出っ張りがついたホームポジション用のキー(写真右)も販売されている。
デフォルトのGlove80のキーキャップには、一般的なキーボードのようにホームポジション(F, J)に出っ張りがない。
しかし、Glove80のお椀型のデザインとパームレストによって、自然とホームポジションに手のひらが導かれるため、レイアウトに慣れるに従って、補助がなくても全く問題なくなっていく。
筆者の場合、初期の頃はタッチタイプ時の安心感のためにもMBKキーキャップを親指キーに、出っ張り付きのキーキャップを人差し指(F, J)に目印的に配置していたが、日に日にGlove80に手が馴染んでいき、徐々に補助の必要性は無くなってきた。
1ヶ月半ほどGlove80を使い込んだ時点で、補助を外してデフォルトのMCCキーキャップのみにしてみたが、特に問題なかった。
特殊配列キーボードに初めて挑戦する初心者の場合、ホームポジション用のMCCキーキャップを追加注文しておくと安心かもしれないが、1ヶ月も使えば慣れるので、必須ではない。
また、JIS用のキーキャップセットも販売されているので、変換キーや記号キーの印字を、日本語キーボードと一致させたい場合には購入すると良いだろう。
キースイッチの選択肢
先述の通り、Glove80は、ロープロファイルのKailh Choc v1 スイッチを採用している。
筆者は様々なメカニカルキーボードを渡り歩いた結果、ハイプロファイルのMXスイッチのキーボードを使用すると、ほぼ確実に指と手首に痛みが生じてしまうことが分かっており、ロープロファイルの恩恵を大いに感じている。指や手首の上下移動の削減効果は、非常に大きいのだと思う。
購入時に選べるキースイッチは、MoErgo限定の2種類の静音軸(Cherry Blossom, Plum Blossom)のほか、一般的なKailh Chocスイッチ4種類(Red, Brown, White, Red Pro)から選べる。
筆者は軽量の静音リニア軸「Cherry Blossom」(30gf)を選んだが、本当に滑らかにタイピングできる。特に打ち間違いが増える等の副作用もないので、指の痛みや腱鞘炎がある人は、これを選ぶのが良いだろう。

軽すぎると嫌な人は、同じく静音リニアの「Plum Blossom」(45gf)や、一般的なKailh Choc軸のタクタイル、クリッキーなどを選ぶ手もある。
湾曲型のメカニカルキーボードでは、構造上、ホットスワップの実装が難しいようで、ホットスワップは非対応だ。
購入後にキースイッチを交換することはできないので、もし購入前に時間の余裕があり、メカニカルキーボード初体験で好みのスイッチが分からないのであれば、Kailh Chocのスイッチテスターを購入して、押し心地を試してから選ぶのが理想だろう。
レイアウトエディタでキー配置の変更も自由自在
Glove80は、「ZMK」というオープンソースのファームウェアを採用している。高度なカスタマイズ性を持ち、キーマップの再プログラミングが可能だ。
キーボード本体の設定自体を書き換えられるので、PC側での設定やアプリが不要で、自宅のPCだけでなく、会社のPCやスマホ・タブレットなどでも、お気に入りのキー配置を使える。
キーレイアウトの変更は、専門知識は一切不要で、ブラウザ上で直感的に使える「Glove80 Layout Editor」が用意されている。
ビジュアルで確認しながらZMKファームウェアを作成・編集できるので、誰でも手軽にZMKの恩恵を受けられるのが魅力だ。

「かな」や「英数」などの日本語特有の特殊キーなども含め、ZMKで利用可能なキーコードはZMK公式の一覧表にまとまっているので、これを見つつ必要なキーを割り当てていく。
個々のキーに好きなアルファベットや記号を割り当てるのはもちろん、長押し/タップの区別で複数の機能を一つのキーに割り当てるなど、豊富な機能がある。
また、「レイヤー」機能も、非常に柔軟なカスタマイズを可能とする重要機能だ。
Glove80では複数の「レイヤー」を設定でき、レイヤーごとにキーレイアウトを変更できる。ゲーム専用のレイヤーや、数字入力専用のレイヤーなどを用意しておけば、作業効率を大きく改善できる。
例えば、デフォルトで用意されているLowerレイヤーでは、右手側をテンキーとして利用でき、Excelなどを使用する際に数値入力が格段に楽になる。

レイヤー間の移動もまた、個々のキーに移動先のレイヤーを割り当てて、長押し中は当該レイヤーに移動する、といった設定をする。

作成したレイアウトをGlove80本体に反映するには、レイアウトエディタから出力した.uf2形式の設定ファイルを、USB接続した左右のGlove80の中にコピーするだけで簡単だ(詳細な手順はユーザーマニュアルで解説されている)。
編集〜本体反映までがスムーズなので、一度変更したレイアウトがしっくりこなくても、再度修正してすぐに試すなど、試行錯誤がしやすい。

ちなみに、公開されているキーレイアウトの中には、英文入力に特化した合理的配列である「DVORAK配列」や、プログラミングに特化した「Glorious Engrammer」など、数多くのGlove80用のキーレイアウトがあるので、中上級者は旧来のQWERTYとは全く異なる配置にチャレンジしてみても良いだろう。
高度な設定例:JIS環境でUSキーボードの印字通りに出力する
「Glove80 Layout Editor」で実現できるカスタマイズの幅をお伝えするため、少しマニアックな設定例を紹介する。
長年US配列のキーボードを愛用してきた筆者は、社用のWindows PCが、US配列であってもJIS配列と認識してしまうため、キーの印字と出力される記号が異なるストレスにずっと悩まされてきた。
例えば、US配列では「Shift + 2」は「@」のはずだが、会社のPCではこれがJISキーボードのように「”」と出てしまうのだ。

こんなケースでも、ZMKのマクロ機能(Custom Behaviors)を使えば、社用PCでもUS配列の出力を実現できる。
「Custom Behaiviors」は、キーの挙動を定義するオリジナルの関数を作成し名前をつけ、それを個々のキーに割り当てられる機能だ。

JISキーボードとUSキーボードの対応表を調べると、USキーボードで[記号を打ち込むと、JIS環境では@記号として認識されることが分かる。
これを逆手に取って、&n2_w_jisというCustom Behaviorを定義し、平時は2を、シフト押下時は[記号を出力するマクロを作って「2」キーの位置に割り当てると、JIS環境でも、US配列キーの印字通りの@を表示してくれる。
behaviors {
n2_w_jis: ansi_n2_and_at_with_jis {
compatible = "zmk,behavior-mod-morph";
label = "ANSI_N2_WITH_JIS";
#binding-cells = <0>;
bindings = <&kp N2>, <&kp LEFT_BRACKET>;
mods = <(MOD_LSFT|MOD_RSFT)>;
};
};「Glove80 Layout Editor」では、Custom Behaviorsの入力欄も用意されているので、究極、独自のあらゆるキー設定が可能である。

なお、ここで紹介したCustom Behaviorsは、noranikoというユーザーの方がGlove80のレイアウトエディタで公開している設定ファイルの中から、抜粋して例を示したものだ。
真似をしたい人は、この設定ファイルをコピーすればいいだけなので簡単だ。また、オリジナルのマクロを作成したい場合も、ChatGPTに「ZMKのCustom Behaviorsを作成して」と言えば、結構いい感じに生成してくれる。
このような設定の自由度の高さや、コミュニティで共有されているユースケースの豊富さもGlove80の魅力である。
技適ありのBluetoothと、バッテリー・USB接続
Glove80は、4台までのデバイスとBluetoothペアリングすることが可能だ。Mac, Windows, iPad, iPhone, Androidなど、OSを問わずペアリングして使うことができる。
そして、嬉しいことに技適マークがついているので、日本でも合法的に使用可能だ。
多くの海外のカスタムキーボードでは、技適が取得されていないか、Bluetooth非対応であることが多いので、国内で無線使用が可能なだけでも、結構希少な選択肢と言える。

左右の両方に独立したリチウムポリマーバッテリーが入っているので、片手だけUSBで給電し、もう一方はバッテリーで利用、といった使い方も可能だ。
5年〜10年と長期間使用する可能性を考えると、バッテリーの寿命を維持することも重要なポイントだが、公式のQ&Aによれば、バッテリーのコネクタを外して、純粋なUSB給電キーボードとして使用することも可能だという。
この辺りの設計も、道具として長持ちすることが意識されているようで心強い。
バッテリーは長期間持つが、RGBを豪華に点灯していると半日程度しか持たないので、RGBを付けっぱなしで作業したい場合はUSB給電するのがおすすめだ。
筆者は、自宅のデスクでは二股USBで両手とも常時USB接続しておき、外出時や出張時にのみ、Bluetoothで使用するようにしている。アクセサリーとして左右を同時に充電できる二股のUSBケーブルも販売されている。
Glove80の使用初日〜1ヶ月超の感想
お椀型、左右分割型、カラムスタッガード配列という究極のエルゴデザインに、果たして自分が適応できるか心配する人もいるだろう。
結論としては、2-3週間もすれば仕事で使えるレベルまで鍛えられるので、あまり心配する必要はない。筆者も、特殊配列を使うのは初体験であったが、意外とすぐ慣れるんだな、という感想だった。
実際に、筆者がGlove80に初めて触った時の感想や、その後タイピングスピードが徐々に上がっていくまでの経過についても紹介しておこうと思う。
Glove80を使い始める前の筆者は、キーボードを目視せずタッチタイピングはできるが、スピードは中級程度だった。
Glove80使用前の旧来のキーボードでのスコアと、Glove80を使った初日、10日後、30日後のスコアの推移は以下の通りだ。
| タイピングテスト | 使用前 | 1日目 | 10日後 | 30日後 |
|---|---|---|---|---|
| 日本語(e-typing) | 369 (Ninja) | 258 (A+) | 384 (Comet) | 430 (Professor) |
| 英語(monkeytype) | 85 wpm | 73 wpm | 86 wpm | 94 wpm |
意外にも、Glove80に移行した初日から、テキストの入力スピードは早かった。旧来のキーボードから、オーソリニア/カラムスタッガード配列への移行自体は、大して難しくない。
どちらかというと、苦労したのは、修飾キー(shift, controlなど)やキーボードショートカットの記憶を上書きすることだ。
ショートカットキーを多用する長文の執筆作業でも、Glove80を完全にストレスなく使えるようになったのは、使用開始から2-3週間が経過してからだった。最初の1-2週は、急ぎの仕事は旧来のキーボードに戻って進めてしまうこともあった。
1ヶ月も使えば、もはや従来の人生最高記録を塗り替えるほど慣れてしまった。
左右スプリットやエルゴノミクスデザインのおかげで、もともと左手より右手の方を優先して使いがちだった悪い癖などが抜けて、効率的な運指が自然にできるようになっていく。
ただし、2-3週間はコツコツ練習することは必須だ。暇な時間があれば、以下のようなタイピング練習サイトで練習するようにしていた。
- e-typing 腕試しレベルチェック(日本語)
- monkeytype(英語と一部記号)
- keybr.com (英語とプログラムコード)
タイピングスピードが早くなってからは、自宅でメイン使用するのはもちろん、オフィスに持って行ったり、出張に持って行ったり、肌身離さず持ち歩いている。
毎日持ち運ぶにはトラベルケースは大きいので、筆者はGlove80をカメララップなどに包んで、バックパックの隙間に入れて持ち歩いている。

日本へも送料無料!簡単に購入できる
Glove80を購入したくなったら、MoErgoの公式サイトで簡単に購入できる。海外からの発送となるが、日本へも送料無料で配送してくれる。
カスタムキーボードの世界は、そもそもの製造数が少ない/個人が販売していることも多く、在庫切れでかなり長期間待たないと購入できないこともよくある。
その点、Glove80は、企業が販売していることもあって安定供給されており、左右スプリット・お椀型というニッチでありながら、非常に入手性も高いのでありがたい。
また、技適に対応していることも含め、日本市場向けのオプションも充実している。
Glove80のデフォルトはUS配列だが、レイアウトエディタで変更すれば、JIS配列キーボードとして利用することもできる。JISキーキャップもオプションとして販売されている。
ちなみに、本体もアクセサリも、販売価格は日本円で表示されているが、輸入に際して消費税がかかるため、販売価格+10%ちょっとの負担を想定しておくと良いだろう。
総合評価:指・手首・肩の疲労感があるPCヘビーユーザーは絶対買うべき

高級なメカニカルキーボードや、HHKBやリアルフォースは魅力的だが、人間工学的には、従来のキーボードと同じ問題を抱えている。結局のところ、どれだけ打鍵音や外観が美しくても、実質的なベネフィットは少ないのだ。
特に、筆者の場合は、超長時間のタイピングによる慢性的な疲労や、ショートカットキーのための不自然な指の伸ばし方が痛みの原因になっていたので、キー設計を根底から変えないと問題が解消されなかった。
「Glove80」は、初期投資としては高級キーボードに分類すべき価格帯だが、今後他のキーボードを買う必要がなくなるし、健康への投資としてリターンは非常に大きいと思う。
使い始めて最初の1-2週間は、新たな配列に慣れる負荷は高いが、それを乗り越えれば、圧倒的にタイピングが快適になるので、PCを仕事にするプロフェショナルなら、挑戦して損はない。
「Glove80」の良い点と留意点をまとめると、以下のようになる。
- 最高なところ
- 肩こりや手首、指の痛みなど、PC作業にまつわる悩み解消
- 長時間タイピングしても本当に疲れない
- 持ち歩くのも可能なサイズ感と身軽さ
- ブラウザ上で使える分かりやすいレイアウトエディタ
- キーキャップの印字と配列を一致させることができレイアウトを覚えやすい
- 矢印キーもあり、修飾キーも多く、意外にも移行の難易度は低い
- 注意点
- 最初の2週間ほどは慣れない配列のストレスあり。数週間はコツコツとタイピング練習を続ける覚悟は必要。
- Glove80に完全に慣れると、通常のキーボードを使うのが億劫になるので、会社などへの持ち歩き方法を要検討。
類似のエルゴノミクスキーボードの選択肢としては、同じく「お椀型」を採用した「Kinesis Advantage」や、それが左右分割型に進化した「Kinesis Advantage360」もよく知られている。
「Kinesis Advantage360」は、そもそもほとんど日本で流通しておらず在庫がないため、購入すること自体が困難だ。また、価格も非常に高額で、Bluetooth対応版は10万円を超え、「Glove80」の1.5-2倍近い価格帯となっている。
その割に、Glove80との価格差を納得できるだけの追加機能があるかというとそんなこともなく、約1.5kgと重いため持ち運びも困難、テンティングも3段階のアングルのみ、キーキャップ同士で形すら異なるためGlove80ほど自由にキーキャップを入れ替えられないなど、あまりメリットがない。
現状、左右分割型でお椀型のレイアウトのエルゴノミクスキーボードを使いたい場合は、間違いなくMoErgo Glove80がベストな選択肢だと言えるだろう。
開示事項:当サイトでのレビューを行うため、筆者からメーカーに連絡を取り、レビュー用端末の提供を受けた。金銭的報酬は一切受領しておらず、すべての評価は筆者の実使用に基づく。